「ピー!ピー!ピー!ピー!・・・」いきなり部屋中に鳴り響くガス警報器!!ガスが漏れたような臭いもないし、煙もない、焦げ臭さもない。慌てて警報器の停止ボタンを押すと、鳴りやんだガス警報器!パンの二次発酵がオーブンで完了し、ほんの数分そのままにしていた矢先の出来事!どうやら、原因は発酵中のパン生地から発生した「ある物質」だったのかもしれません!
この記事では、なぜ発酵中のパンで警報器が鳴ったのか?その衝撃の体験談から、イーストのガスが原因である可能性、そして二度と同じ体験しないための具体的な対策までを調べましたので、パン作りをする人は、ぜひ最後まで読んでください!
パン二次発酵時にガス警報器が作動!?
とある早朝、一次発酵までをホームベーカリーでし、そこから形を成形。生地にハム入れ、形を整え、40℃に設定したオーブンの中にパンを入れ、二次発酵へ。

オーブンの機能を使い、40℃前後の密閉空間で約40分間の発酵をかけていました。40分発酵し終わって、数分の間オーブンに入れたままにしていたら、いきなり「ピーピーピーピー」とガス警報器が作動!慌てて停止ボタンを押して鳴りやみましたが、パン作り中にガス警報器がなるなんて、初めてのことで、鳴りやまなかったらどうしよう!って、不安になりました。
ガス警報器が鳴った原因はなに?イーストの臭いが関係あるの?
ガス漏れもしていないのに、なぜ「ガス警報器」は鳴ったのでしょうか?ガス警報器が反応する物質について調べ、原因を探ってみました!
ガス警報器が鳴った原因
私たちの家にある、ガス警報器は、主に都市ガス(メタンなど)やLPガスを検知します。そして、実はアルコール(エタノール)などの可燃性ガスにも反応することがあるんです!
パン生地を密閉して発酵させる際、
二酸化炭素とともにエタノール(アルコール)を生成するんです。このエタノールが揮発し、警報器が『ガス漏れ』と誤検知した可能性が高いのです。
また、アルコールガスは空気より重いため、天井の都市ガス用警報器でも床のLPガス用警報器でも反応する可能性が十分にあります。ただし、誤検知するからといって、ガス警報器を一時的に覆うのは危険なため推奨はできません。

へぇ~!!こんなことってあるんだね!!発酵すると二酸化炭素とエタノールを生成するのもビックリ!
イーストの臭いは関係あるの?
パンの発酵で警報器が鳴った時、イーストの独特な臭いがあったので、「イーストの臭い」が原因だったのでは?と考える人もいるかもしれませんよね。
しかし、ガス警報器が反応した直接的な原因は、イーストの「臭い」ではないんです。
警報器が反応したのは、イーストの「臭い」ではなくて、パンを発酵させたときに出る「ガス」が原因なんです。
分かりやすく見ていきましょう♪
| 物質名 | 役割・特徴 | 警報器への影響 |
| エタノール | イーストが糖を分解する際に生成される 可燃性ガス。警報器が検知する物質。 | 主たる原因。揮発したエタノールガスがガス漏れと誤検知された。 |
| 二酸化炭素 | 生地を膨らませるガス。 | 警報器の誤作動には直接関係ない。 |
| イーストの臭い成分 | 発酵中に生成される微量のエステルやアルデヒドなど。パン特有の香りのもと。 | 警報器が「ガス漏れ」として検知する可燃性ガスではない |
つまり今回、警報器が鳴った原因は、イーストそのものの臭いではなく、イーストの活動によって生成・揮発したエタノール(アルコール)ガスが警報器に反応するレベルにまで達してしまい、このような事が起きてしまったのでしょう。
同じ体験をしないための対策
ガス警報器の作動は、エタノールガスの発生によるものだと分かりました。パン作りを安全に楽しむために、二度と警報器を鳴らさないための具体的な対策を見ていきましょう。
対策1:二次発酵時の環境の見直し
密閉空間で発酵させるとガスの濃度が上がりやすくなります。警報器を設置している場所での発酵時には、必ず換気を徹底すること。
・オーブンを置いている部屋の換気扇を必ず回す。窓を少し開けて、空気の通り道を作るのも効果的。
・警報器から遠い場所で発酵させる。または発酵器や発泡スチロール箱など、換気のしやすい小さな密閉空間を別に作る。
対策2:アルコールガスを過剰に発生させない発酵の工夫
エタノールガスは、過発酵(発酵のしすぎ)やイースト量が多い場合に、特に大量に生成されやすい。パン生地の調整で、発生するガスを減らすこともできるので、量を調整するのも一つ。
・発酵温度が高すぎると、発酵が急激に進み、アルコールが過剰に発生しやすくるので、適切な発酵温度(目安:30~40℃)を厳守し、過発酵を防ぐ。
・発酵時間を守ること。設定時間を超えて放置しないように、時間がきたら次の工程に進むようにする。
・イーストの量が多すぎないか?レシピのイーストの量も確認すること。イーストを増やしすぎると、その分アルコール生成も増えてしまう。
対策3:警報器が鳴った時の対処法
警報器が鳴った時は、ビックリするかもしれませんが、冷静に対応すること。
・警報器が鳴ったからといって、コンセントから抜くのはやめましょう。
・誤作動が明らかな場合は、慌てず停止ボタンを押して警報を止めること。そしてすぐに窓を開けて換気を行うこと。

お住まいの警報器が「都市ガス用」か「LPガス用」か、また「複合型(CO検知機能付き)」かの確認もしておくのもいいかも!!
まとめ
今回は、パン二次発酵の時にガス警報器が鳴り、原因はなんだったのか?そして警報器が鳴った時の対策を以下にまとめました。
・ガス警報器が鳴った原因は、パン生地の発酵中にイーストが生成するエタノール(アルコール)ガスが、警報器にガス漏れとして誤検知されたという可能性が高い。
・「イーストの臭い」ではなく、発酵時に生成した可燃性ガスであるエタノールが密閉空間で高濃度になったことが臭いの原因だった可能性が高い。
・ガス警報器の作動を防ぐ対策は、二次発酵時の換気徹底と、過発酵を防ぐ時間・温度管理が最も重要だということ。
まさか、パンの二次発酵でガス警報器を鳴らすとは、思ってみませんでしたが、ある意味、イーストがしっかりと働き、パン生地が活発に発酵している証拠でもあるのだな~と思いました。
今回、初めての体験でしたが、ガス警報器が鳴ったことにより、正しい知識と具体的な対策を実践すれば、警報器が鳴る心配なく、美味しいパン作りを楽しむことができると思いました。
同じような体験をされた方、もしくは、これからパン作りをする方のお役に少しでも立てれると幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

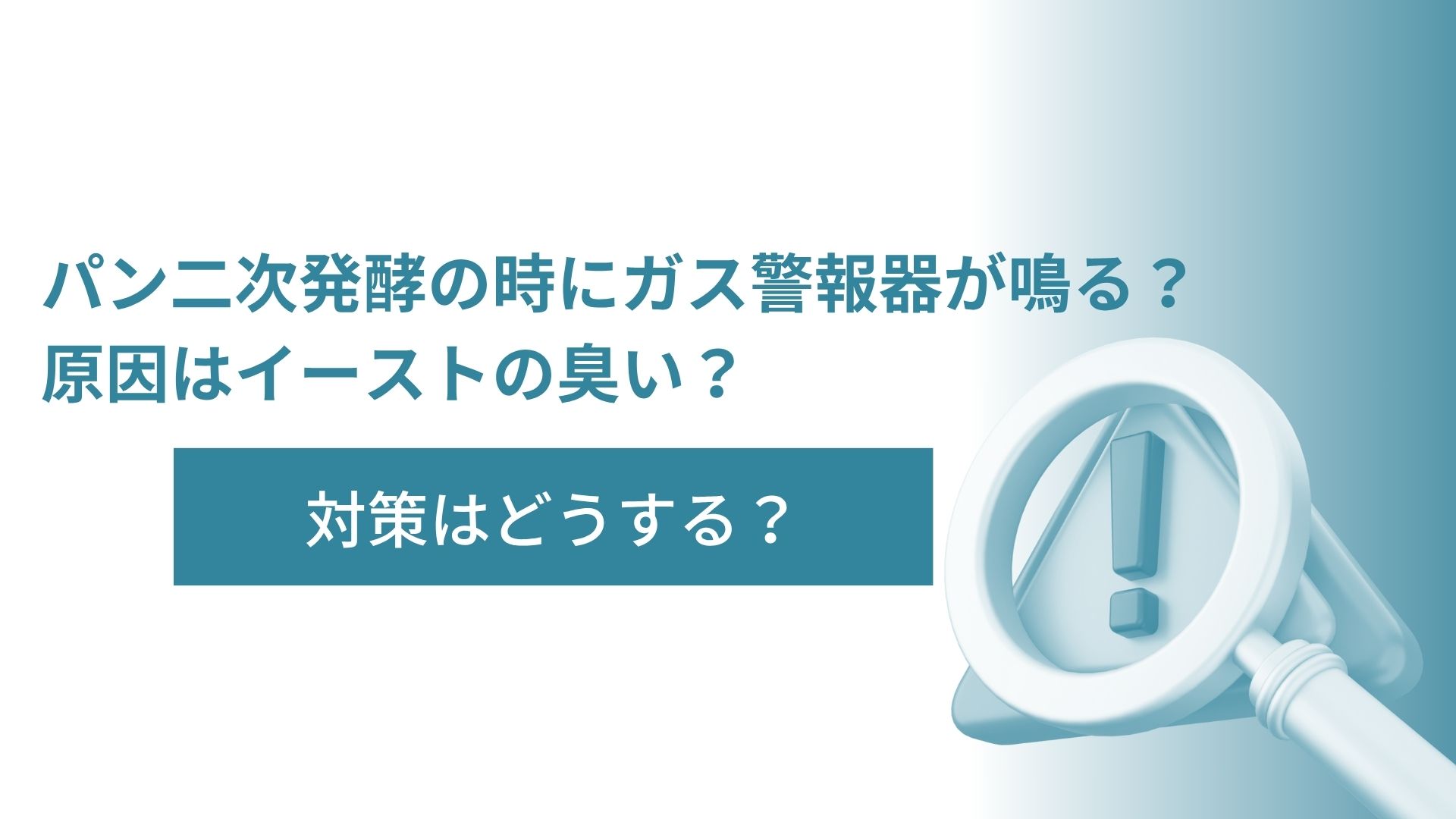

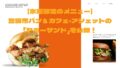
コメント